[ジャンル] 宗教・思想
28件 講座中 1~10件目を表示
-
Newおすすめ入会金必要常時入会可
生き方としてのマインドフルネスー新瞑想としても注目 NHK全国放送にも講師が登場 1月から新クール
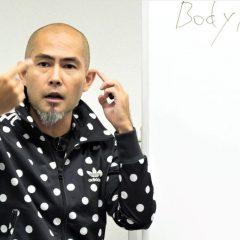 Newおすすめ入会金必要常時入会可
Newおすすめ入会金必要常時入会可「あいつ、マインドフルネスはじめるってよ」。 NHKで2023年3月、4月に放映された番組「あいマイ」(https://www.nhk.jp/p/ts/JMGY3WPNVR/schedule/te/G56276VJMP/?area=270)では、当講座担当の小室弘毅講師が登場しました。 また、NHKの全国放送番組「トリセツショー」でも、マインドフルネスが「新瞑想(めいそう)」としても取り上げられるなど、さらなる注目を集めています。 マインドフルネスは、痛みやストレスの低減、うつの再発予防、創造性開発、集中力向上といった効果があるとされ、医療、心理、教育、スポーツ、ビジネスと多くの領域で研究が進められています。 「新瞑想」としても注目 本やテレビでは学べない体験を 本講座では、「新瞑想」としても注目を浴びるマインドフルネスを、初学の方にも、すでに実践されている方にも、新しい視点で理論と体験を提供し、コツをお伝えできたらと考えています。 マインドフルネスは単なる技法にとどまるものではなく、「生老病死」という私たちの生の全体性に関わるもの、生きることの柱となるものです。そういった意味でのマインドフルネスを理解するため には、科学的な知見だけでなく詩や小説、アートといった生を全体として捉える人文学的な視点が必要となってきます。 本講座では、人文学の中でも特に人の成長にかかわる教育人間学の視点から、仏教思想や心理学も援用しつつ、講義と実習を行います。2025年12月までの旧クールと、タイトルは同じですが、内容的には新規の講義になります。 1 月17日 マインドフルネスとは? 2 月14日 マインドフルネスの背景 3 月14日 方法としてのマインドフルネス 4 月11日 マインドフルネスと身体 5 月 9日 思想としてのマインドフルネス 6 月13日 生き方としてのマインドフルネス ■講師プロフィール 東京大学大学院教育学研究科で「教養=自己形成」についての研究をスタートし、からだとこころの関係から人間形成の問題を探求している。近年はヨーガ、ボディーワーク、身体心理療法、マインドフルネス研究へと対象領域を広げ、教育における身心のあり方を探っている。

関西大学人間健康学部教授 小室 弘毅

関西大学人間健康学部教授 小室 弘毅
-
Newおすすめ入会金必要
九星気学入門
 Newおすすめ入会金必要
Newおすすめ入会金必要★2026年1月スタート★ こんな方におすすめ ・九星気学を基礎から学びたい ・占いを趣味にしたい ・開運のヒントを生活に取り入れたい ・運気の仕組みを知りたい ・人間関係を客観的に見たい 九星気学とは、生まれた年に宿る“気”のエネルギーから、その人の性質・思考パターン・運気の流れ・行動のタイミングを読み解く東洋の占いです。五行理論を基に日本で発展し、性格・運勢・方位の吉凶など、日常に活かしやすいのが特徴です。引っ越しや旅行、開店日などの良いタイミング選びにも役立ちます。まずは生年月日から九星を導き、自分の傾向を知ることからはじめてみましょう。スマホやタブレットを使えば、九星や方位も簡単に調べられるので、初心者でも気軽に学べる占術です。 ■紅京花先生による「運勢鑑定」(要予約) ・日時:原則第1・第3日曜13時00分~15時30分(最終枠15時00分) ※鑑定時間は1案件または1名分で30分程度。最終枠15時20分。実施日・時間枠・空き状況はお問い合わせください。 ・鑑定料:1案件または1名分 4,000円(現金のみ・当日支払い) ・申込:センター受付またはお電話にてご予約を承ります。 ※命式準備のため、予約時に「鑑定してほしい方の氏名(正確な漢字表記)・性別・生年月日・出生時間」をお伺いします。出生時間は分からなくても鑑定可能ですが、あった方がより正確な結果が出せます。 ・締切:実施日2日前の正午(前週金曜)

日本運命学易占学院学院長 紅 京花

日本運命学易占学院学院長 紅 京花
-
Newおすすめ入会金不要
雅楽と法話の世界へようこそ 三管両絃 ~音色とことばのひととき~
 Newおすすめ入会金不要
Newおすすめ入会金不要プログラム内容 ・雅楽ってどんな音楽? ~楽器紹介とお話~ ・法話トークセッション「仏教と雅楽のつながり」 ・雅楽演奏「平調 音取」「平調 越殿楽」「平調 陪臚急」他 5名で奏でるおだやかな音色と、優しいことばに包まれて 心がほぐれる時間をお過ごしください。 「琵琶弾けるの俺しかおらんねん」 2025年大阪・関西万博に、1日だけ登場した、多様な仏教表現を融合させたお寺「万博寺(ばんぱくじ)」で楽琵琶を演奏した水谷了義さんをはじめ、柱本惇さん、埜上孝樹さん、阿満慎介さんをお呼びして、特別に演奏をして頂きます。 出演者の皆様が所属する「聲明と雅楽」の会 響音<Kyо-оn>より1名を加え、総勢5名の僧侶が 「楽琵琶」「楽筝」「鳳笙」「篳篥」「龍笛」を奏でます。 三管両絃の雅楽と法話の特別講演を、ゆっくりとお楽しみください。 奏者 楽琵琶(がくびわ) 水谷了義(浄土真宗本願寺派 順照寺 住職) 楽筝(がくそう) 柱本惇(浄土真宗本願寺派 明覺寺 住職) 鳳笙(ほうしょう) 古川奈都 (浄土真宗本願寺派 満行寺 衆徒) 篳篥(ひちりき) 埜上孝樹(浄土真宗本願寺派 東坊 住職) 龍笛(りゅうてき) 阿満慎介(浄土真宗本願寺派 西養寺 衆徒) ※会場は、毎日新聞ビルB1 うめだMホール です。 【会場住所】 大阪市北区梅田3丁目4番5号B1 西梅田地下道「6-10」出入口より、毎日新聞ビルB1階にご入館できます。

浄土真宗本願寺派 順照寺 住職 水谷了義 他 総勢5名

浄土真宗本願寺派 順照寺 住職 水谷了義 他 総勢5名
-
Newおすすめ入会金必要
インドから日本へ ブッダの教えを読みとく新シリーズ
 Newおすすめ入会金必要
Newおすすめ入会金必要人気講座の新シリーズです! 「ブッダの教えを読みとく」、10月からの新シリーズのテーマは「インドから日本へ」。 インドで始まった仏教は長い時間をかけて、南はスリランカから東南アジアへ、北は中央アジアを経て中国大陸、朝鮮半島、そして日本へと伝えられました。時代や文化の影響を受けながら、柔軟に姿を変え、今日まで受け継がれてきた仏教の歩みをたどります。 2015年10月から開講している「ブッダの教えを読みとく」は、半年(全6回)ごとにテーマを変え、様々な角度からブッダの教えを解説し、仏教理解を深める講座です。今シリーズは20期目となります。 【カリキュラム】(予定) 1 仏教の始まり ーインド 2 仏教の南伝 ースリランカ・東南アジア 3 仏教の北伝 ー中央アジア 4 仏教の東漸1 ー中国 5 仏教の東漸2 ーチベット・モンゴル 6 仏教の東漸3 ー日本

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実
-
Newおすすめ入会金不要
ギャンブル 行動症(依存症)
 Newおすすめ入会金不要
Newおすすめ入会金不要1|ギャンブル行動症(依存症)とは? ・なぜ「やめたいのにやめられない」状態が起きるのか ・依存症にまつわる誤解と本当のこと 2|なぜギャンブル行動症になるのか ・脳と行動のメカニズム ・ネットカジノ、IR、競馬、パチンコに共通する“仕組み” 3|ギャンブル行動症の治療の実際 ・医療機関で行われるサポート ・家族・周囲ができる関わり方 ・回復までの道のり 4|ギャンブル行動症の研究 ・最新の研究動向 ・効果的とされる支援方法 ギャンブル依存症を正しく知る ネットカジノ・IR(統合型リゾート)・競馬・パチンコなど、身近な娯楽として広く楽しまれているギャンブル。しかし、その“楽しさ”がきっかけとなり、生活や人間関係に深い影響をおよぼす「ギャンブル行動症(依存症)」へつながることがあります。この講座では、専門知識がなくても理解できるよう、ギャンブル行動症の基礎から最新の治療・研究までをやさしく解説します。

京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座(精神医学)病院講師 鶴身 孝介

京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座(精神医学)病院講師 鶴身 孝介
-
Newおすすめ入会金不要見学不可
人間ドラマで読み解く 地動説の歴史
 Newおすすめ入会金不要見学不可
Newおすすめ入会金不要見学不可古代より普及していた天動説に対する科学⾰命としての地動説は、16世紀のコペルニクスから始まり、17世紀のケプラー、ガリレオへと受け継がれます。 地球が宇宙の中⼼にあって不動であると信じられていた時代に、いかにして地動説が⽣まれ、発展していったのかを、科学者たちの波乱万丈の⼈⽣をたどりながら解説します。 科学の歴史と⼈間ドラマをお楽しみください。

美術史・科学史研究家 松本 佳子

美術史・科学史研究家 松本 佳子
-
New入会金必要常時入会可
おもしろい!心理学入門
 New入会金必要常時入会可
New入会金必要常時入会可2025年10月開講! 心理学はみなさんにとって最も身近な学問の1つです。 私たちの日常生活の中に、「心の世界」への入り口がたくさん存在しています。 本講座では、身近ではあるけれども、おもしろく不思議な、だけど普段は見逃しがちなトピックを取り上げます。 勘違いや見間違い、ストレス対処の個人差、つい空気を読んでしまう心理など…身近で気になるテーマをわかりやすく紹介します。 さらに、そもそも「おもしろい」とはどういうことか、笑いが心身に与える効果や、クラウン(道化)のユーモアが持つ不思議な力にも迫ります。 心理学を楽しく学びたい方にぴったりの全6回――知的で愉快な学問の世界をご一緒しましょう 2025年10月~2026年3月カリキュラム予定 ① 10月25日(土) いきなり入門!心理学の裏話:「余談」が一番面白いのはなぜ!? ② 11月22日(土) 感情とストレスの心理学:あなたにぴったりの対処法を見つけよう! ③ ※ 12月6日(土) 自分らしさの心理学:空気を読む私、本音はどこにある? ④ 1月24日(土) 勘違いの心理学:錯覚・思い込み・誤解のメカニズム ⑤ 2月28日(土) ユーモアの心理学①:『笑う門には福来る』は本当か? ⑥ 3月28日(土) ユーモアの心理学②:笑いを魅力に変える道化の力 ※2025年12月の講座日は、講師出張のため、急きょ日程を変更することになりました。 2025年12月27日(土)は休講で、12月6日(土)に行います。時間帯は同じです (2025/11/22記入) ご参照 臨床心理学と社会 (2025年4月~9月開講) 本講座では、実践的な学問である臨床心理学を通じて、多角的な視点から現代社会のさまざまな課題を読み解く知見をご紹介します。 教育現場の課題、多様化する家族とその諸問題、大転換期を迎えた司法領域、SNSによるつながりと混乱の時代、そしてAIがもたらす心理学の未来――これらのテーマについて、具体的事例や最新の研究知見を交えながら掘り下げていきます。日常生活に役立つ心理学的アプローチや用語を解説しつつ、社会と心の関係を深く考察していきましょう。 2025年4月~9月カリキュラム予定 4月26日(土) 第1回 序論: 臨床心理学から社会課題を考えるために 5月24日(土) 第2回 教育と臨床心理学: 学校現場の課題と心の支援 6月28日(土) 第3回 家族問題と臨床心理学: 多様化する家族への心理的アプローチ 7月26日(土) 第4回 犯罪と臨床心理学: 司法領域の大変化と再犯防止への取り組み 8月23日(土) 第5回 SNSと臨床心理学: 新しい”つながり”を取り戻すために 9月6日(土) 第6回 AIと臨床心理学: 心のケアを担う未来のかたち ※2025年9月27日(土)は講師の都合で9月6日(土)に日程変更になりました。時間帯は同じ13:00~15:00です

神戸学院大学講師、臨床心理士、公認心理師 岡村 心平

神戸学院大学講師、臨床心理士、公認心理師 岡村 心平
-
Newおすすめ入会金不要見学不可途中入会不可
高野山に伝わる 真言密教の文化・美術 ―弘法大師空海が伝えた品々に込められた意義―
 Newおすすめ入会金不要見学不可途中入会不可
Newおすすめ入会金不要見学不可途中入会不可真言密教とは、弘法大師空海によって開かれた真言宗において説かれる教えのことです。そもそも真言密教は神秘性・象徴性・儀礼性といった要素を強く持ち、多種多様な経典や密教法具、また僧侶のきらびやかな衣装などに特徴があります。 そこで本講座では、特に真言密教における経典や仏像、法具などの品々にスポットを当て、画像や実物をもとに解説していきます。 カリキュラム 2月24日 真言密教の経典 ―『般若心経』解説と読誦― 真言宗のみならず、日本の多くの仏教宗派には、日常的に『般若心経』を読誦する文化があります。一方で、経典は唱えさえすればよいのではなく、その意味を理解してお唱えすることも大切です。そこで『般若心経』をひも解き、真言密教における独自の解釈についても解説します。 3月17日 真言密教の仏像・仏画 ―高野山の阿弥陀如来を中心に― 真言密教では、曼荼羅に代表されるように多種多様な仏たちを説きます。 それらを仏像や仏画として表現しますが、仏像・仏画は単なる美術品ではありません。そこで仏像・仏画とは一体いかなるものかを、高野山に伝わる阿弥陀如来を一例として御紹介します。 3月24日 真言密教の仏具 ―真言宗の法具や袈裟にふれる― 真言宗の寺院では、荘厳(しょうごん)具と呼ばれる華麗な飾りや袈裟などの衣装、さらにさまざまな密教法具を目にすることができます。本講座では、それらの宗教的・美術的意義を解説するのみならず、実際に荘厳具や袈裟などの実物にふれていただきます。 袈裟や法具などを間近で見て触れることができる貴重なチャンスです!!

高野山大学准教授 北川 真寛

高野山大学准教授 北川 真寛
-
おすすめ入会金必要常時入会可
『歎異抄』の世界
 おすすめ入会金必要常時入会可
おすすめ入会金必要常時入会可『歎異抄』とは、浄土真宗の宗祖・親鸞が語った言葉を、門弟の唯円が書き記した書物です。この書は仏教の難解な論理がまとめられているのではなく、門弟と悩みを共有しながら真摯に仏道を歩む、人間親鸞の飾らない姿が書き留められています。 かつて日本歴史文学の巨匠・司馬遼太郎が「無人島に1冊の本を持っていくとするなら歎異抄」と述べたのは有名なお話です。井上靖や五木寛之など、多くの文学者に影響を与え、日本の仏教書の中で最も読まれている『歎異抄』の内容を読み解いていきます。 ① 11月24日 第6条~親鸞は弟子一人ももたず~ ② 12月 8日 第7条~無碍の一道~ ③ 1月26日 第8条~他力の念仏~ ④ 2月23日 第9条前半~唯円房のふたつの問い~ ⑤ 3月23日 第9条後半~凡夫の情をつつむ大悲~
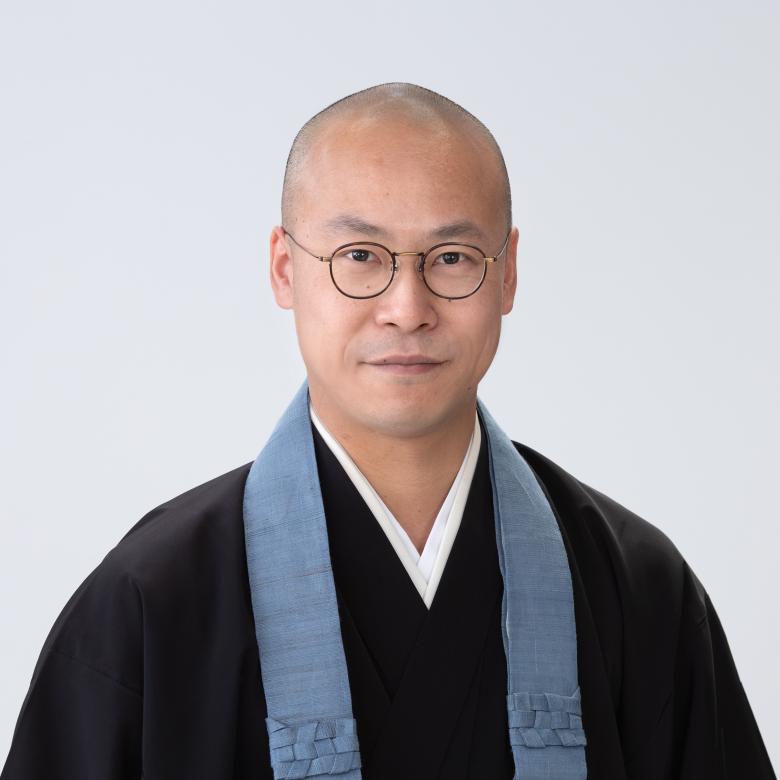
相愛大学非常勤講師 四夷 法顕
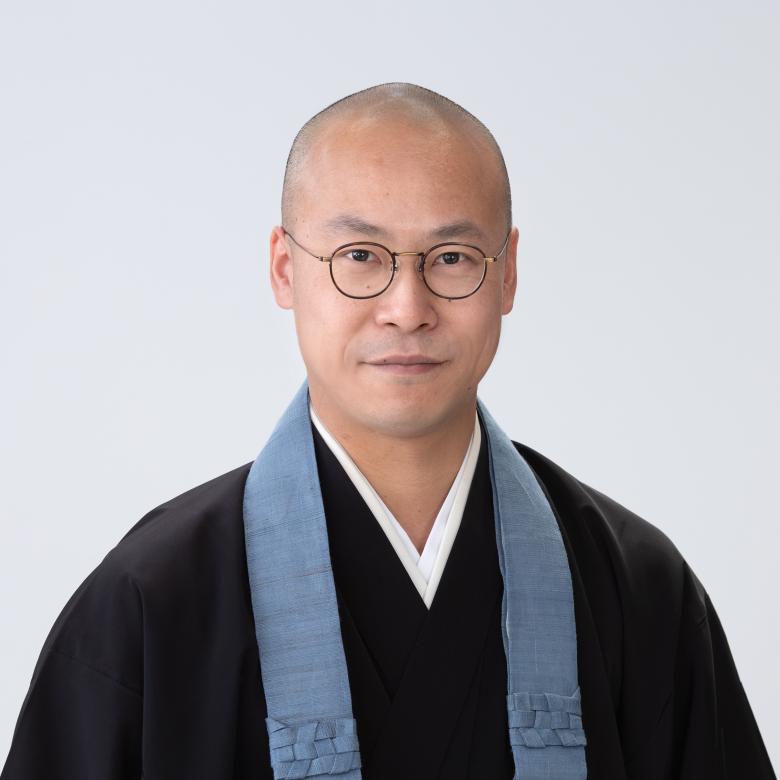
相愛大学非常勤講師 四夷 法顕
-
New入会金必要
仏教の原点
 New入会金必要
New入会金必要仏教というものを、「宗教」という枠組みから外し、仏教最古層に属する経典『スッタニパータ』を通して、ブッダの肉声に迫ります。 仏教の原点に触れ、仏教とはいったいいかなる教えであるかを探って行きます。

高野山大学名誉教授 前谷 彰(恵紹)

高野山大学名誉教授 前谷 彰(恵紹)















