[ジャンル] おすすめ講座
60件 講座中 51~60件目を表示
-
Newおすすめ入会金必要常時入会可
親鸞聖人の和讃を読む
 Newおすすめ入会金必要常時入会可
Newおすすめ入会金必要常時入会可親鸞聖人の「和讃」を一首ずつ取り上げて、その短い言葉に込められた深い内容を紐解いていきます。 お経やその註釈書をもとにして、仏様や高僧方のお徳を讃え、法味豊かな七五調の歌にしたものを「和讃」といいます。 親鸞聖人は、生涯で五百四十首以上もの和讃を制作されました。中でも『浄土和讃』『高僧和讃』『正像末和讃』は三帖和讃と呼ばれ、浄土真宗の法義が余すところなくおさめられていると言われています。 この三帖和讃を通して、阿弥陀仏のおこころを味わってまいります。 第一回 和讃概説 第二回 高僧和讃 源信讃① 源信僧都の略歴 「源信和尚ののたまはく」「本師源信ねんごろに」 第三回 高僧和讃 源信讃② 源信僧都の教義(報化二土) 「霊山聴衆とおはしける」から「極悪深重の衆生は」まで 第四回 高僧和讃 源空讃① 源空聖人の略歴①(立教開宗) 「本師源信世にいでて」から「承久の太上法皇は」まで 第五回 高僧和讃 源空讃② 源空聖人の教義(信疑決判) 「諸仏方便ときいたり」「真の知識にあふことは」 第六回 高僧和讃 源空讃③・総結 源空聖人の略歴②(ご臨末) 「源空光明はなたしめ」から「本師源空命終時」まで 高僧和讃総結 「五濁悪世の衆生の」

浄土真宗本願寺派吉祥寺住職、行信教校講師、本願寺派宗学院研究員、本願寺派布教使 西村一樹

浄土真宗本願寺派吉祥寺住職、行信教校講師、本願寺派宗学院研究員、本願寺派布教使 西村一樹
-
おすすめ入会金必要常時入会可
椅子座禅とブッダの教え 椅子座禅の実地体験と禅の言葉を読む
 おすすめ入会金必要常時入会可
おすすめ入会金必要常時入会可椅子坐禅(正身端坐)の実践と、禅の言葉を読むの2本柱です。 体育室で椅子座禅を実地体験し、一番古いお経(アッタカヴァッガ)を講師がバーリ語原典から現代日本語に訳した本『 ブッダの言葉』と、最初期の禅僧の最も重要な言葉を集めた本『禅の言葉』をじっくり 読み味わっていきます。 厳しくつらい座禅ではないので、どなたでも気軽にご受講いただけます。

天正寺住職 元臨床心理士 佐々木 奘堂

天正寺住職 元臨床心理士 佐々木 奘堂
-
入会金必要常時入会可
囲 碁 ~プロ最高段位九段に教わろう!
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可囲碁のプロ最高位の九段、矢田直己先生に学べ、指導も受けられるお勧めの講座です。 タイトル戦の「本因坊」で最終予選まで勝ち進むなど、一線で活躍する矢田先生。 講座での分かりやすい説明は定評があります。 順次、指導碁も受けられます。 受講は毎月、受け付けています。 ★初級・中級コース★ ルールはある程度覚えたが、実戦経験が少ない方に適した講座です。見知らぬ人と対戦する勇気が持ちにくいとお考えの方や、9級~4級ぐらいの実力をお持ちの方向けの講座です。対局も随時行っていきます。半年カリキュラムで1級前後を目指します ★上級・有段コース★ 受講生の方が対局した内容を徹底して問題点を探り出し、上達を目指します。

関西棋院九段 矢田 直己

関西棋院九段 矢田 直己
-
おすすめ入会金必要常時入会可
「文章楽屋」 実用スキルを添削指導で
 おすすめ入会金必要常時入会可
おすすめ入会金必要常時入会可文章を書くのが苦手、書き方がわからないという人、大歓迎です。むずかしいことはしません。役者が舞台裏の楽屋でくつろぐように、講師も受講者も和気あいあいで進めます。「文章楽屋」。ぶんしょうがくや、ぶんしょうらくや、です。 毎回、宿題として800字の作文を書いていただきます。LINE、メール、または原稿用紙で講師に提出。添削・講評後、全員で共有し、次回の教室で意見交換します。言葉や文章をめぐる、時々の話題の解説、うんちくも楽しんでください。 年齢、性別、職業不問。これまでの教室には、20~80代と幅広い年代の方々が集ってくださいました。 講師は全国紙の元編集委員です。歴史考古学や伝統宗教が主な担当で、わかりやすく柔らかな文章表現を得意としています。ちなみに好きな作家は沢木耕太郎、浅田次郎、景山民夫、吉村昭、山本周五郎、藤沢周平など。主な著書に『ご先祖様も被災した 震災に向き合うお寺と神社』(岩波書店、単著)『髙田長老の法隆寺いま昔』『阿修羅像のひみつ』(以上朝日新聞出版、共著)があります。 手紙、エッセイから小論文、就活エントリーシートまで、幅広く使える書き言葉の技をお教えします。 ※いつからでも入会可です。

全国紙元記者・編集委員、文化財ジャーナリスト 小滝 ちひろ

全国紙元記者・編集委員、文化財ジャーナリスト 小滝 ちひろ
-
Newおすすめ入会金必要
東アジアの中の古代日本 ―古代東アジア交流史―
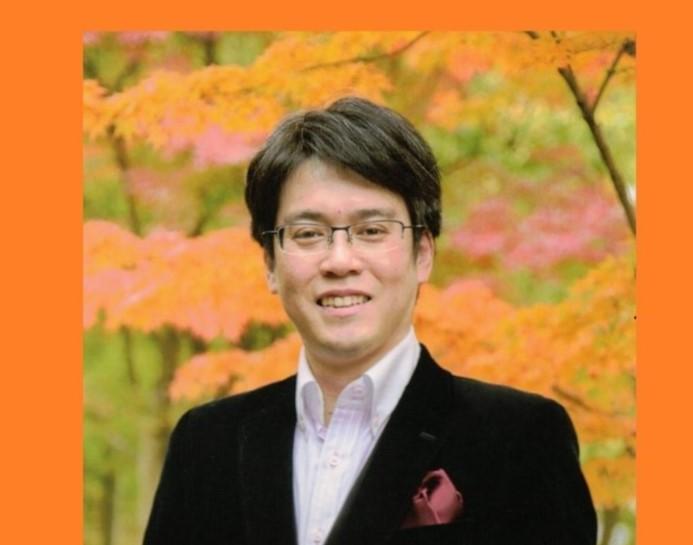 Newおすすめ入会金必要
Newおすすめ入会金必要―古代東アジア交流史― 古代日本にとっての「世界」とは、中国・朝鮮半島といった東アジア文化圏でした。 日本でおこった歴史的事件も、実は多くそれらの地域と密接な関係を持っています。 なぜ大化の改新は起こったのか? 遣隋使はなぜ7世紀に始まったのか? 遣唐使の真の役割は? 従来の視点とは違う、東アジア史の視点から日本の古代史を再検討してみましょう 2025年4月~9月カリキュラム予定 4月8日(火) 第一回 邪馬台国 5月13日(火) 第二回 倭の五王 6月10日(火) 第三回 遣隋使 7月8日(火) 第四回 遣唐使 7月29日(火)※ 第五回 天平文化 9月9日(火) 第六回 国風文化 ※8月12日は休館日のため、7月29日(火)に変更します

京都女子大学教授 藤本 猛

京都女子大学教授 藤本 猛
-
入会金必要常時入会可
デジタル写真教室
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可「思いが伝わる、心が響く写真」を撮ってみませんか。一眼レフのデジタルカメラやミラーレスカメラの操作方法、その仕組みなど、楽しく基本から丁寧にお教えします。基本を学んだあとは、復習しながら撮影を行い、操作の習熟を図ります。野外での撮影会も行っており、その次の回には野外で撮影した写真のデータやプリントの講評を行います。教室と現地撮影を交互に3回ずつ(5、7、9、11、1、3の奇数月は野外)。皆さん一緒に上達していきましょう。6カ月6回のワンクールが終わった後も、ワンクールずつ更新していけば、どんどん上達していきます。※上記写真は講師作品。

写真家 岩本 哲仁

写真家 岩本 哲仁
-
おすすめ入会金必要常時入会可
楽しくフォトめぐり 撮影会と講評会で腕を磨く
 おすすめ入会金必要常時入会可
おすすめ入会金必要常時入会可初めてカメラを購入された方や、カメラは持っているけれど使い方に不安のある方、自分の思うように撮影できないといったお悩みをお持ちの方にもおすすめです。 カメラの使い方から、撮影のちょっとしたコツなど、撮りたいものを自分のイメージ通りに撮れる様になるためのアドバイスやポイントをわかりやすくご紹介します。 講師の作例や受講生の写真を見ながら楽しく基礎を学び、1カ月2回のうち1回は、季節に合わせた撮影実習を行います。次の回には品評と指導を教室でという2回1セットのサイクルです。 身の回りにあふれる素敵なものや瞬間を、お気に入りの写真に残しませんか。

フォトグラファー 喜屋武 愛子

フォトグラファー 喜屋武 愛子
-
New入会金必要
道鏡 悪僧と呼ばれた男の真実
 New入会金必要
New入会金必要写真:弓削神社(八尾市東弓削) 奈良時代の僧侶・弓削(ゆげ)の道(どう)鏡(きょう)は、女帝に取り入った野心家として長く悪名が根付いているが、本当にそのような人物だったのでしょうか。 さまざまな伝説の検証や、史料の綿密な検討によって、古代政治の実態を描き出します。 大阪府八尾市で、女帝・称徳天皇ゆかりの由義寺(弓削寺)跡が発掘されるなど、近年見直されている話題の人物です。 講師の著書『道鏡』に沿ったカリキュラムで、実際には政治に関与することなく、天皇への仏教指導に終始した人物としての意外な実像が見えてくる過程を丁寧に解説します。 2025年4月~9月 4月15日(火)第1講:うわさの道鏡 5月20日(火)第2講:道鏡と仏教の出会い 6月17日(火)第3講:道鏡と律令国家 7月15日(火)第4講:称徳朝政治と道鏡 8月19日(火)第5講:称徳天皇の崩御と道鏡の左遷 9月16日(火)第6講:律令天皇制における道鏡

元和歌山市立博物館館長 寺西 貞弘

元和歌山市立博物館館長 寺西 貞弘
-
入会金必要常時入会可
英語で読む『春にして君を離れ』
 入会金必要常時入会可
入会金必要常時入会可ミステリーの女王、アガサ・クリスティーがメアリ・ウェストマコットという名で書き上げた作品で、評価が高く近年注目を浴びてきた人気のAbsent in the Springを読んでいきます。 主人公はエルキュール・ポアロでもミス・マープルでもなく、ロンドン郊外に暮らす女性で夫を支え子供たちを立派に育て上げ理想の家庭を築いてきたと自負しています。娘の見舞いに訪れた異国の地の帰りに、偶然女学生時代の友人と出会い話をするうちに、ふと、自分の人生は自分が思っているような人生だったのかと疑問を持ち始めます。足止めされた砂漠で過去を振り返り、記憶をたどっていくうちに、理想と思っている人生は、ただ自分が見たいように見ていた人生ではなかったのか…真実から目をそらしていたのではないか…と思い始めていきます。 殺人も起こらず探偵も登場しませんが、さすがにクリスティーの作品だけあって、真実が徐々に浮かび上がっていく過程には、ミステリー感サスペンスにあふれています。クリスティーが本当に書きたかった一作ではないかと思います。 読みやすい小説です。原文を味わい、読み手それぞれの思いと照らし合わせながら楽しんで読みましょう。

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子
-
New入会金必要常時入会可
おもてなし茶道 裏千家 入門・小習・四ケ伝合同
 New入会金必要常時入会可
New入会金必要常時入会可大徳寺黄梅院や天王寺公園内慶沢園、公益財団法人有斐斎弘道館などで茶会を開催し、自宅で茶道教室も主宰する講師による「入門・小習・四ケ伝合同」の講座です。月3回 第1・2・3火曜、 16:00~20:00の間の約2時間をお選びいただけます。 【開講日】 月3回 第1・2・3火曜 16:00~20:00の間の約2時間 【持ち物】 懐紙、菓子楊枝、替え足袋(白ソックス)、扇子、ふくさ、ふくさ挟み

裏千家准教授 太城宗優

裏千家准教授 太城宗優















