[ジャンル] 歴史
51件 講座中 1~10件目を表示
-
満席
1回1駅めぐり旅 環状線を制覇する 外回り編
 満席
満席※満員御礼 キャンセル待ち受付中です JR大阪環状線は全19駅。 その発車メロディーが全て違うことは、とても有名です。 それ以外にも、各駅に潜む秘密や歴史がたくさんあります。 大阪らしいユーモアと謎があふれる環状線を、 1駅ごとに深掘りしてみませんか? 毎回、現地を歩きながらのフィールドワークです。 駅周辺のまち歩きも行います。 各駅に、オリジナルスタンプもあります。 スタンプ帳をぜひお持ちください。 コンプリートを目指しましょう!

大阪まち歩き大学学長 まち歩きプロデューサー 陸奥 賢

大阪まち歩き大学学長 まち歩きプロデューサー 陸奥 賢
-
New入会金必要常時入会可
原文で味わう英米小説 『万国博覧会』 (World’s Fair,1985)
 New入会金必要常時入会可
New入会金必要常時入会可【講師】英米文学博士 橋本 万里子 【開講日】2026年4月1日スタート 第1・3水曜 13時~14時30分 【受講料】3カ月6回 16,500円 映画化された作品『ラグタイム』『ビリー・バスゲイト』でも知られるアメリカの作家E. L.ドクトロウの自伝的といえる小説を原文で味わいます。 この作品は、大恐慌の名残りから第二次世界大戦へと世界が大きく変わっていく1930年代のニューヨーク、ブロンクスに暮らす少年の目を通して家族を語り、ニューヨークを生き生きと描きアメリカそして世界を垣間見ます。家族にも世界にも徐々に暗雲が立ちこめていく中、クライマックスは「明日の世界の建設と平和」をテーマにした1939年の「ニューヨーク万国博覧会」へと向かいます。 講読期間中何度か、小説中に描かれるニューヨークの町並みを講師撮影の写真でスライド鑑賞し、より深く作品の世界に入っていきましょう。 テキスト】 World’s Fair by E. L. Doctorow ・出版社 Random House, New York, 2007. ・ISBN-13 : 978-0-8129-7820-9 (現在3500円) 「万国博覧会」をご受講されるみなさまへ 本講座では、解説しながら英語原文を読み進めていきます。単なる訳読ではなく、豊富な資料から背景にある時代や社会、文化を学び、より深い内容理解を目指します。講座は、講義形式で行います。英語レベルは高校生程度としていますが、興味があれば特に問いません。 ・2026年4月から始まり、約2年程度で読了予定です。受講料は3カ月単位ですが、講座は継続して行っています。見学をご希望の場合は、初回2026年4月1日以外の日程で、15分程度となります。 ・本講座では指定の原書が必要ですので、ご自身で購入ください。当センターでの販売は行っておりません。お持ちでない場合は、初回の講座で講師にご相談ください。原書のコピーをお渡ししますので、原書がお手元に届くまでコピーをご持参ください。

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子

英米文学博士 英語学校講師 橋本万里子
-
Newおすすめ入会金不要見学不可
公開講座『古事記』説話と『日本書紀』 ~大物主神を巡る説話を読む~
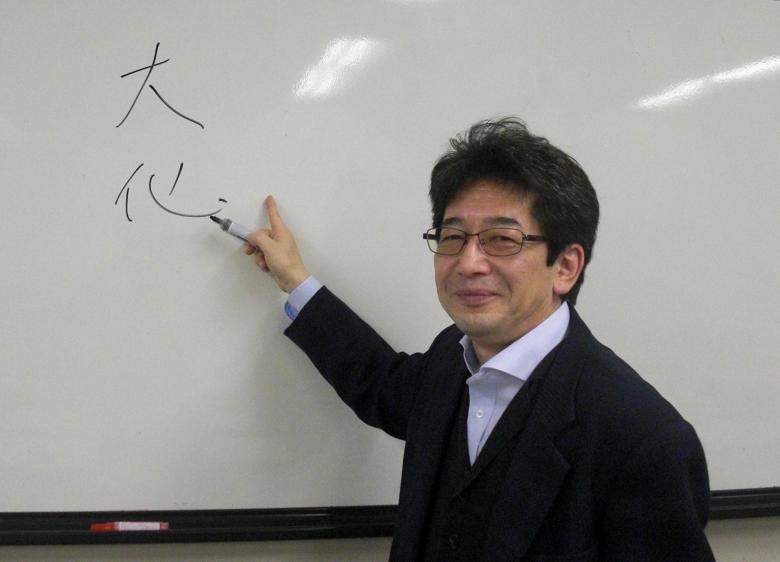 Newおすすめ入会金不要見学不可
Newおすすめ入会金不要見学不可『古事記』は、日本に残されているもっとも古い歴史書のひとつです。神話から書きはじめられ、読み親しまれている方も多いと思います。しかし同時代に編まれた『日本書紀』と読み比べるとその内容はずいぶん違い、日本に残されていた話が一つではなかったことがわかります。 今回は『古事記』中巻、初代神武天皇代が大物主神の娘と結婚する話から、第10代崇神天皇に至ると大物主神が祟る話までを、『日本書紀』を交えながら読みます。 はじめての方でも大丈夫、現代語訳で読みやすい資料を講師が準備します。筆記用具だけで気軽にお越しください。 2/17 大物主神の娘との結婚 3/3 欠史八代の不思議 3/17 大物主神の祟り
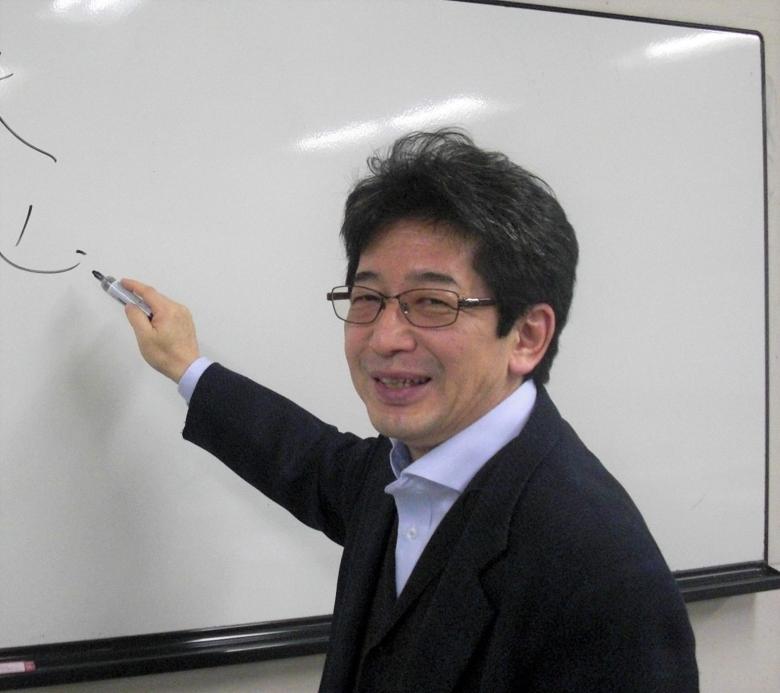
梅花女子大学教授 市瀬 雅之
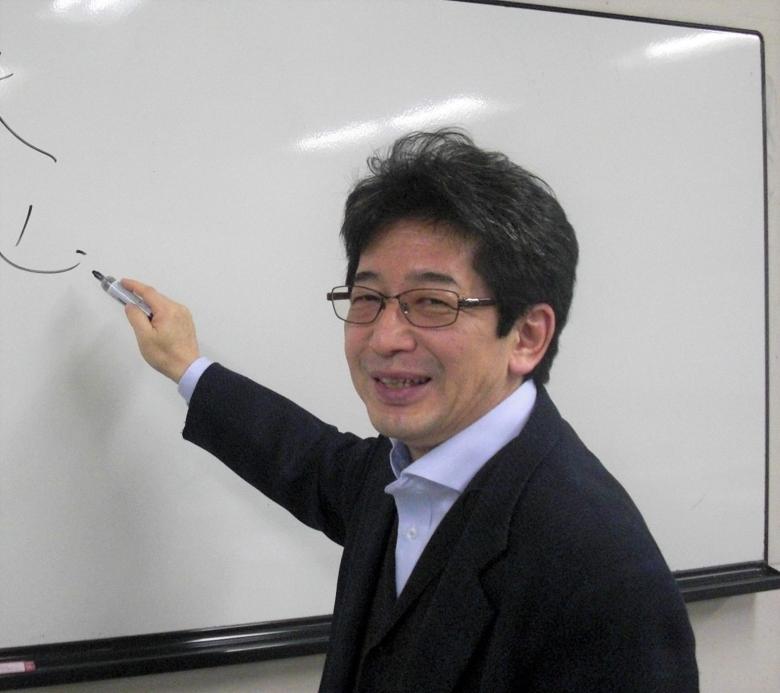
梅花女子大学教授 市瀬 雅之
-
Newおすすめ入会金必要常時入会可
藤原一族の陰謀 新講座!2026年4月7日開講!
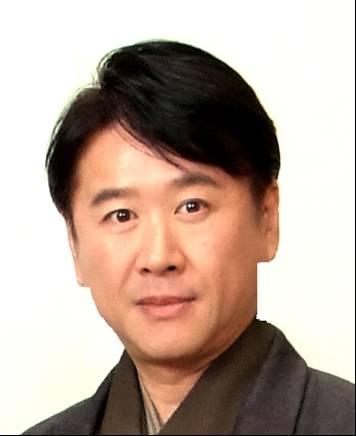 Newおすすめ入会金必要常時入会可
Newおすすめ入会金必要常時入会可日本史上最大の氏族である藤原氏。 いつから、どのようにして権力を持ち、日本を支配していったのでしょうか? 藤原氏がしかけた陰謀の数々を壮大なスケールでお話します。 歴史好きな方も詳しくない方も映画を見るように楽しんでいただけます。 4/7 藤原鎌足の陰謀 ~乙巳の変~ 6/2 藤原不比等の陰謀~弓削皇子の死~ 6/30 藤原四兄弟の陰謀~長屋王の変~ 7/7 藤原仲麻呂の陰謀~奈良麻呂の変~ 8/4 藤原百川の陰謀~井上皇后の暗殺~ 9/1 藤原種継の陰謀~早良親王の廃位
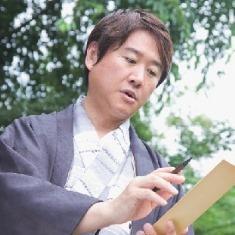
現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長 林 和清
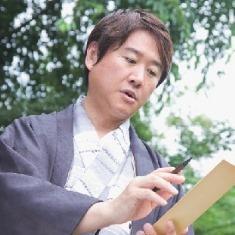
現代歌人協会会員・現代歌人集会理事長 林 和清
-
Newおすすめ入会金不要
雅楽と法話の世界へようこそ 三管両絃 ~音色とことばのひととき~
 Newおすすめ入会金不要
Newおすすめ入会金不要プログラム内容 ・雅楽ってどんな音楽? ~楽器紹介とお話~ ・法話トークセッション「仏教と雅楽のつながり」 ・雅楽演奏「平調 音取」「平調 越殿楽」「平調 陪臚急」他 5名で奏でるおだやかな音色と、優しいことばに包まれて 心がほぐれる時間をお過ごしください。 「琵琶弾けるの俺しかおらんねん」 2025年大阪・関西万博に、1日だけ登場した、多様な仏教表現を融合させたお寺「万博寺(ばんぱくじ)」で楽琵琶を演奏した水谷了義さんをはじめ、柱本惇さん、埜上孝樹さん、阿満慎介さんをお呼びして、特別に演奏をして頂きます。 出演者の皆様が所属する「聲明と雅楽」の会 響音<Kyо-оn>より1名を加え、総勢5名の僧侶が 「楽琵琶」「楽筝」「鳳笙」「篳篥」「龍笛」を奏でます。 三管両絃の雅楽と法話の特別講演を、ゆっくりとお楽しみください。 奏者 楽琵琶(がくびわ) 水谷了義(浄土真宗本願寺派 順照寺 住職) 楽筝(がくそう) 柱本惇(浄土真宗本願寺派 明覺寺 住職) 鳳笙(ほうしょう) 古川奈都 (浄土真宗本願寺派 満行寺 衆徒) 篳篥(ひちりき) 埜上孝樹(浄土真宗本願寺派 東坊 住職) 龍笛(りゅうてき) 阿満慎介(浄土真宗本願寺派 西養寺 衆徒) ※会場は、毎日新聞ビルB1 うめだMホール です。 【会場住所】 大阪市北区梅田3丁目4番5号B1 西梅田地下道「6-10」出入口より、毎日新聞ビルB1階にご入館できます。

浄土真宗本願寺派 順照寺 住職 水谷了義 他 総勢5名

浄土真宗本願寺派 順照寺 住職 水谷了義 他 総勢5名
-
Newおすすめ入会金必要
インドから日本へ ブッダの教えを読みとく新シリーズ
 Newおすすめ入会金必要
Newおすすめ入会金必要人気講座の新シリーズです! 「ブッダの教えを読みとく」、10月からの新シリーズのテーマは「インドから日本へ」。 インドで始まった仏教は長い時間をかけて、南はスリランカから東南アジアへ、北は中央アジアを経て中国大陸、朝鮮半島、そして日本へと伝えられました。時代や文化の影響を受けながら、柔軟に姿を変え、今日まで受け継がれてきた仏教の歩みをたどります。 2015年10月から開講している「ブッダの教えを読みとく」は、半年(全6回)ごとにテーマを変え、様々な角度からブッダの教えを解説し、仏教理解を深める講座です。今シリーズは20期目となります。 【カリキュラム】(予定) 1 仏教の始まり ーインド 2 仏教の南伝 ースリランカ・東南アジア 3 仏教の北伝 ー中央アジア 4 仏教の東漸1 ー中国 5 仏教の東漸2 ーチベット・モンゴル 6 仏教の東漸3 ー日本

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実

博士(文学),宗教情報センター研究員、京都大学非常勤講師、大阪大学非常勤講師 佐藤 直実
-
Newおすすめ入会金必要
天皇陵からみた古代日本
 Newおすすめ入会金必要
Newおすすめ入会金必要2025年10月開講! 大阪や奈良を歩いていると鳥居のあるこんもりとした山を見かけることがよくあります。これは古代の天皇のお墓です。 宮内庁の陵墓調査官だった講師が、古墳、陵墓、古代の天皇を解説しながら、日本古代史の諸問題を解き明かします。 2025年10月~2026年3月カリキュラム予定 第1回(10/14)「天皇陵とは何か -陵墓の概論(名称・所在地・種類・数)-」 第2回(11/11)「天皇陵治定(ちてい)の歴史 -陵墓の管理と祭祀-」 第3回(12/9)「天皇陵治定の確からしさ -古墳時代研究と天皇陵-」 第4回(1/13)「仁徳天皇陵の調査と研究 -日本最大の古墳における調査と成果-」 第5回(2/10)「八角形墳の天皇陵 -最後の天皇陵古墳とその歴史的背景-」 第6回(3/10)「天皇陵の巡拝 -人々と天皇陵、陵墓の未来-」
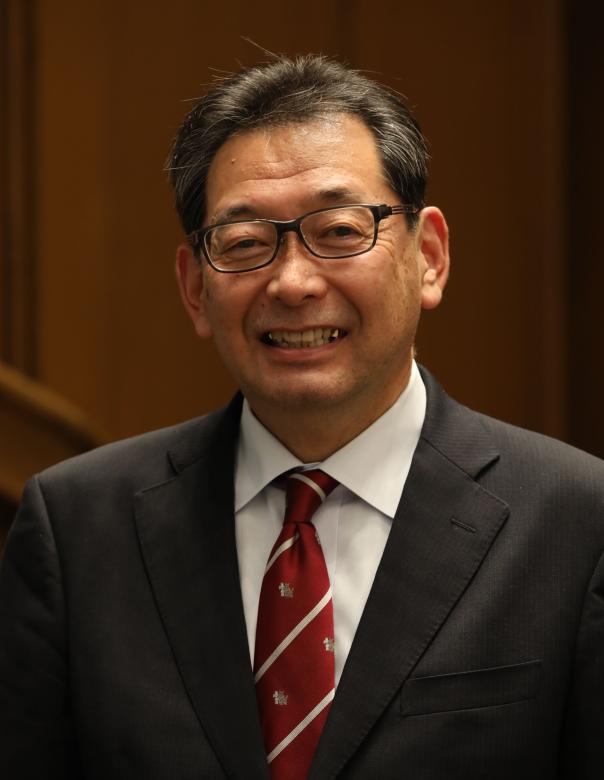
関西大学客員教授・国士館大学客員教授 徳田 誠志
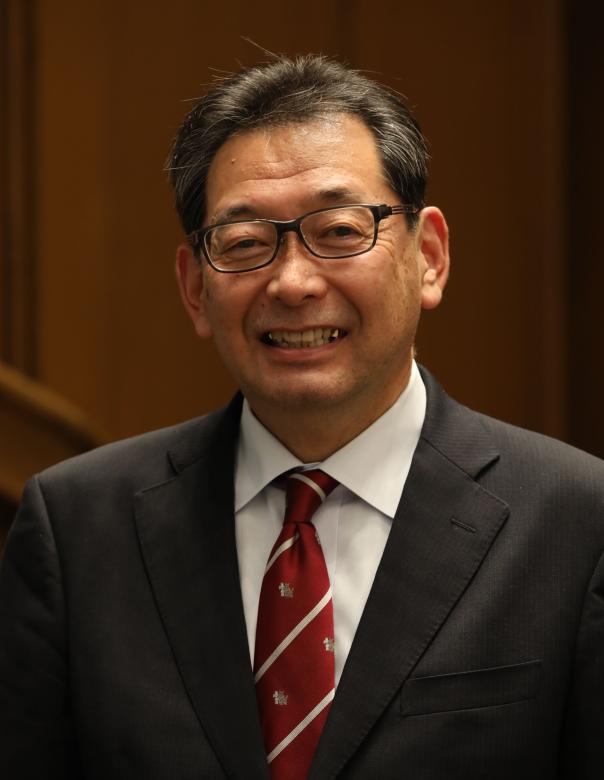
関西大学客員教授・国士館大学客員教授 徳田 誠志
-
New
『万葉集』に名を残した人物とその生涯
 New
New日本各地に『万葉集』の歌碑が立てられています。歌を残した人々は歌人としての生涯だけを過ごしたわけではありません。天皇であったり、政治家、役人であったり。一般人でありましても時の政策にかかわり、歩いた地やその時の想いを歌に残しています。 彼等の歌がうまれたその時代を共に見てみたいと思います。 2026年1月~6月★カリキュラム予定★ 1月26日(月) 大伴家持 2月23日(月) 倭建命 3月23日(月) 高市皇子 4月27日(月) 柿本人麻呂 5月25日(月) 雄略天皇 6月22日(月) 長屋王

帝塚山大学考古学研究所特別研究員 甲斐 弓子

帝塚山大学考古学研究所特別研究員 甲斐 弓子
-
Newおすすめ入会金不要見学不可
人間ドラマで読み解く 地動説の歴史
 Newおすすめ入会金不要見学不可
Newおすすめ入会金不要見学不可古代より普及していた天動説に対する科学⾰命としての地動説は、16世紀のコペルニクスから始まり、17世紀のケプラー、ガリレオへと受け継がれます。 地球が宇宙の中⼼にあって不動であると信じられていた時代に、いかにして地動説が⽣まれ、発展していったのかを、科学者たちの波乱万丈の⼈⽣をたどりながら解説します。 科学の歴史と⼈間ドラマをお楽しみください。

美術史・科学史研究家 松本 佳子

美術史・科学史研究家 松本 佳子
-
Newおすすめ入会金必要
江戸時代藩校の魅力 漢学 藩校における中国文化
 Newおすすめ入会金必要
Newおすすめ入会金必要藩校とは江戸時代、各藩によって設立・経営され、藩士の子弟育成のための学校です。藩黌(はんこう)、藩学、藩学校とも言います。各藩が人材養成に力を入れ、ほとんどの有力大名が藩校を設け、発展期を迎え、全国255校をも数えました。初期の藩主の学問所や招へいされた碩儒の家塾的なものから、組織・校舎などが整備され、総合的教育のための藩の重要な施設となりました。学習内容は「文武兼備」を目標としましたが、実際には文の比重が大きいです。年少で入学し、まず文を学び、15歳前後から武をも学ぶ例が多いです。学習の中枢は漢学で、すべての藩学で行われており、初学者にも四書五経などの儒学書の素読と習字を課しました。 藩校は藩士の忠誠心を養う人格陶冶から、藩の富国強兵のための時務に通ずる吏僚の知識技能を培う実学教育を目ざす方向に進んでいきました。また、結果として地方文化の振興にも貢献しました。1871(明治4)年の廃藩置県で廃止され、一部は公私立の専門学校、中学校、小学校に変わりました。藩校は日本の教育の原点です。 第4期は、赤穂藩(兵庫県)「博文館」、姫路藩(同)「仁寿山黌」、土佐藩(高知県)「教授館」、島原藩(長崎県)「稽古館」、松前藩(北海道)「徽典館」=写真、佐倉藩(千葉県)「成徳書院」を取り上げます。 【開講日】2026年1月31日(土) 2月以降第1土曜 13時半~15時 【講 師】胡 金定(甲南大学名誉教授、一般社団法人・日中文化振興事業団代表理事) 【受講料】6カ月6回 1万6500円 *文化センターの常設講座が初めての方は別途、入会金が必要です。 第1回 1月31日(第5土曜) 赤穂藩「博文館」=兵庫県 博文館は藩儒だった赤松滄洲・蘭室親子によって計画され、藩主・森忠興によって1777年に現在の「鶴の丸公園」(上仮屋南)に開校。漢学と武芸を主教科とし、藩内の武家の子弟が教育を受けました。残っている平面図によると、講堂、学寮、練武場があったとされます。1872(明治5)年の学制発布後は「博文小学校」となり、現在の赤穂小学校へと系譜がつながっています。 第2回 2月7日 姫路藩「仁寿山黌」=同 仁寿山黌は姫路酒井家家老・河合道臣(寸翁)が建てた私塾です。1821年藩政改革の功績により藩主・酒井忠実から幡下山(はたしたやま)を与えられ、仁寿山黌の建設を開始し、1822年に完成しています。仁寿山という名は、前藩主・忠道が論語の「子曰、知者楽水、仁者楽山、知者動、仁者静、知者楽、仁者寿」から名付けられました。 第3回 3月7日 土佐藩「教授館」=高知県 土佐藩8代藩主・山内豊敷(とよのぶ)が1760年に常設の藩校として創設しました。9代藩主・豊雍(とよちか)は教授館(こうじゅかん)と改称しました。谷真潮、宮地春樹、戸部良煕などが教授役で、朱子学を中心に藩士の教育にあたりました。13代藩主・豊煕(とよてる)まで熱意をもって館を運営してきましたが、豊煕没後は急速に衰えました。 第4回 4月4日 島原藩「稽古館」=長崎県 島原藩は1793年、学術振興のため、「稽古館」を開きました。開校にあたり藩主は、「自今、士卒族の男子齢八歳より入校、学に就くべし。業に奉仕する者は勤務の余暇に登校し、会読、講義を聴講すべし」と布達しています。学科は徳行、経学、文学、史学、国学、律学、兵学、医学、天文学の9科目ありました。授業のあるのは原則として1カ月のうち、4と9のつく日で、月に6回、午後3時開講、月謝は無料でした。 第5回 5月2日 松前藩「徽典館」=北海道 1821年、幕府は直轄をやめて蝦夷(えぞ)全島を松前氏にかえしました。復領後は、かつてあった上級家臣の場所知行を廃止して全島を藩直領とし、藩校「徽典館(きてんかん)」を創立して人材養成をはかり、蝦夷地の警備体制を強化します。「徽典館」の名称は、1805年福島県にできた藩学校に、大学頭・林衡によって選ばれました。この「徽典」という語句は、書経舜典の「慎徽五典」(慎みて五典を徽くす)から採ったもので、人倫五常の道を修める所という意味。松前藩の藩校にも同じ名前が付けられました。 第6回 6月6日 佐倉藩「成徳書院」=千葉県 房総地方最大の佐倉藩の藩校「成徳書院」は医学、武術、兵学、砲術その他いっさいの教育を行い、現在の総合大学に相当する教育機関となりました。成徳書院には8~14歳の幼年者が入学しましたが、そのうち城内居住の藩士の師弟は西塾へ、城外居住の藩士および一般庶民の子弟は東塾で学びました。成徳書院は1871年の廃藩置県により廃止となりましたが、その伝統の一端は、現在の千葉県立佐倉高校に受け継がれています。

甲南大学名誉教授・一般社団法人日中文化振興事業団代表理事 胡 金定

甲南大学名誉教授・一般社団法人日中文化振興事業団代表理事 胡 金定















