[ジャンル] 歴史
52件 講座中 11~20件目を表示
-
入会金必要
金石文・海外史料から日本古代史を考える
 入会金必要
入会金必要2025年10月開講! 『古事記』・『日本書紀』は天皇とヤマト王権を中心とした古代の歴史を伝えています。ここでは、そうした古代国家の形成過程を描いた歴史書から離れて、同時代史料として価値の高い内外の金石文史料や別の立場で外から倭国・ヤマト王権のことを描いている海外の史料から、日本の古代国家の形成過程について考えます。そこから、日本古代の国家と社会についてどのような姿を描き出すことができるのか、新たな視点を加えて分析と解明を進めます。 2025年10月~2026年3月【カリキュラム予定】 10月3日 倭国と百済・高句麗の関係 11月7日 倭王武(雄略天皇)と中国南朝・宋の交渉 12月5日 埼玉稲荷山古墳鉄剣金象嵌銘文 Ⅰ 1月30日 埼玉稲荷山古墳鉄剣金象嵌銘文 Ⅱ 2月6日 江田船山古墳大刀銀象嵌銘文・ 隅田八幡神社所人物画像鏡 3月6日 埼玉稲荷山古墳鉄剣金象嵌銘文 Ⅲ ※2026年1月2日は休館日のため、1月30日(金)に変更します 10月:「倭国と百済・高句麗の関係」 …朝鮮半島の高句麗・長寿王が父の業績を称えた広開土王(好太王)碑文(中国吉林省集安)と、奈良県天理市に鎮座する石上神宮が所蔵する国宝「七支刀」の銘文から、四世紀後半から五世紀初めの、倭国と百済・高句麗の関係を考えます。 11月:「倭王武(雄略天皇)と中国南朝・宋の交渉」 …五世紀の倭国は、讃・珍・済・興・武の五人の王が続けて、中国・南朝の宋に遣使、朝貢を重ねました。積極外交の時代ですが、五人目の武王は478年に遣使したのを最後に、日・中外交は600年の遣隋使派遣まで中断します。倭王武が478年に宋の皇帝に捧げた長大な上表文が、宋の歴史書『宋書』に記されています。この上表文を中心にして、五世紀の日・中外交について考えます。 12月:「埼玉稲荷山古墳鉄剣金象嵌銘文」Ⅰ …埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した国 宝の鉄剣には115字の銘文が刻まれています。これは、五世紀後半だけでなく、ヤマト王権の実態を考える上でも、第一級の重要史料と言えます。今回はその中の「辛亥年・獲加多支鹵大王・八代の系譜・オホヒコの人物像」に焦点を当てて論じます。 1月:「埼玉稲荷山古墳鉄剣金象嵌銘文」Ⅱ …埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した国宝の鉄剣には115字の銘文が刻まれています。今回はその中の「乎獲居臣・杖刀人首の職掌・銘文鉄剣は下賜刀か否か」という問題に焦点を当てて論じます。 2月:「江田船山古墳大刀銀象嵌銘文・隅田八幡神社所人物画像鏡」 …熊本県和水町の江田船山古墳出土の国宝の大刀にも「獲加多支鹵大王世」をはじめとした75字の銀象嵌銘文が刻まれています。また和歌山県橋本市の隅田八幡神社所蔵が所蔵する国宝の人物画像鏡にも48字の銘文が刻されています。そこから「埼玉稲荷山古墳銘文に見える乎獲居と江田船山古墳大刀銘文に見える牟利弖の共通点と相違点・獲加多支鹵大王世の統治の実態」、「癸未年と大王・継体天皇関連の史料となり得るか否か」等の問題に視点を定めて論じます。 3月:「埼玉稲荷山古墳鉄剣金象嵌銘文」Ⅲ …埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した国宝の鉄剣には115字の銘文が刻まれています。今回はその中にみえる「大王」号が「天皇」号成立以前の倭国王の正式称号であったか否かについて検討し、さらに銘文の「治天下」の歴史的意味について追究します。

元龍谷大学文学部教授、博士〈文学〉 平林 章仁

元龍谷大学文学部教授、博士〈文学〉 平林 章仁
-
New入会金必要
豊臣政権の盛衰と大坂の陣Ⅰ
 New入会金必要
New入会金必要2026年4月開講! 豊臣秀吉の天下統一とその歴史的意義を通年にわたって考えていきます。 4月からの前期では、秀吉の生い立ちから始まり、さまざまな経験を積み重ねたのち、織田信長の下で頭角を現したのち、本能寺の変を契機として天下人としての歩みを進め、天下統一を果たす過程を追っていきます。豊臣秀長をはじめとして、秀吉を取り巻く人々との関係も眺めていきます。 豊臣政権の盛衰と大坂の陣Ⅰ ★2026年4月~9月★ 1.4月1日(水) 秀吉の出自と親族 2.5月6日(水) 秀吉と信長―仕官の経緯と戦歴― 3.6月3日(水) 毛利攻めと本能寺の変 4.7月1日(水) 秀吉の覇権闘争―賤ヶ岳から小牧・長久手の戦い― 5.8月5日(水) 聚楽第行幸と豊臣政権 6.9月2日(水) 天下統一と豊臣政権の仕組み 豊臣政権の盛衰と大坂の陣Ⅱ ★2026年10月~2027年3月★ 1.10月7日(水) 文禄・慶長の役 2.11月4日(水) 秀吉の死と豊臣政権の分裂 3.12月2日(水) 関ヶ原合戦 4.1月6日(水) 慶長年間の国制 5.2月3日(水) 大坂の陣 6.3月3日(水) 豊臣政権の歴史的意義 ご参照 「吉宗の享保改革と18世紀の日本」2025年10月~2026年3月 18世紀は日本にとって豊饒の時代でした。 その劈頭をなす徳川吉宗の享保改革では、能力主義人事や国産開発が展開し、続く平賀源内と田沼政治はその継承発展でもありました。経済・文化の問題もふくめて日本の近代化を準備したこの時代を概観します。 ★2025年10月~2026年10月のスケジュール★ 1. 10月1日(水) 徳川吉宗の将軍継承と享保改革 2. 11月5日(水) 能力主義による昇進制度 3. 12月3日(水) 薬種国産化と蘭学の勃興 4. 1月7日(水) 平賀源内とその時代 5. 2月4日(水) 田沼意次の政治 6. 3月4日(水) 田沼政権の倒壊と寛政改革

国際日本文化研究センター名誉教授 笠谷 和比古

国際日本文化研究センター名誉教授 笠谷 和比古
-
Newおすすめ入会金必要
古墳時代の畿内と地方勢力 古代史入門講座
 Newおすすめ入会金必要
Newおすすめ入会金必要2026年4月開講! 三世紀から七世紀のヤマト王権が地域勢力と連合・対峙しながら、どう成立・展開したのか考えます。考古学研究と『古事記』・『日本書紀』研究の成果から、論争や新説を解説します。古代国家とは連合政権? 絶対王権? 各地域の王墓と近畿の古墳を比較します。 講座はスライドショーが中心で、初級レベルの解説をめざします。各回、それぞれ独立したテーマ・内容です。持参いただくテキストなどは特にありません。カラー印刷のレジュメ配布 ★2026年4月~9月全6回 (各10:30~12:00) 第一回 4/26(日) 総論・畿内と大和王権の勢力範囲 第二回 5/24(日) 筑紫(つくし)の勢力とヤマト王権 第三回 6/28(日) 吉備(きび)の勢力とヤマト王権 第四回 7/26(日) 出雲(いずも)の勢力とヤマト王権 第五回 8/23(日) 近江・北陸の勢力とヤマト王権 第六回 9/27(日) 東海・関東の勢力とヤマト王権 ご参照 「ヤマト王権の陵墓古墳を探る」 発掘成果などから、三~七世紀の陵墓古墳とその被葬者像を検討します。話題となっている百舌鳥・古市古墳群、今城塚古墳などの調査成果も解説します。考古学研究と記紀研究との整合、不整合から論争の行方を解説できればと思います。 講座はスライドショーが中心です。写真や図面を多用し、初級レベルの解説をめざします。各回、それぞれ独立した内容です。持参いただくテキストなどは特にありません。 V★2025年10月~2026年3月全6回 (各10:30~12:00) ※11月は第4週ではなく、5週の11月30日(日)ですのでご注意ください 第一回 10/26(日) 総論 陵墓古墳研究の現状と課題 第二回 11/30(日)※ 箸墓古墳・崇神陵古墳・景行陵古墳 第三回 12/28(日) 成務陵古墳・日葉酢媛陵古墳・神功陵古墳 第四回 1/25(日) 応神陵古墳・仁徳陵古墳・履中陵古墳 第五回 2/22(日) 武烈陵古墳・継体陵古墳 第六回 3/22(日) 欽明陵古墳・崇峻陵古墳・推古陵古V

日本考古学協会会員 西川 寿勝

日本考古学協会会員 西川 寿勝
-
New入会金必要
南都仏教の説話 ― 日本霊異記 ―
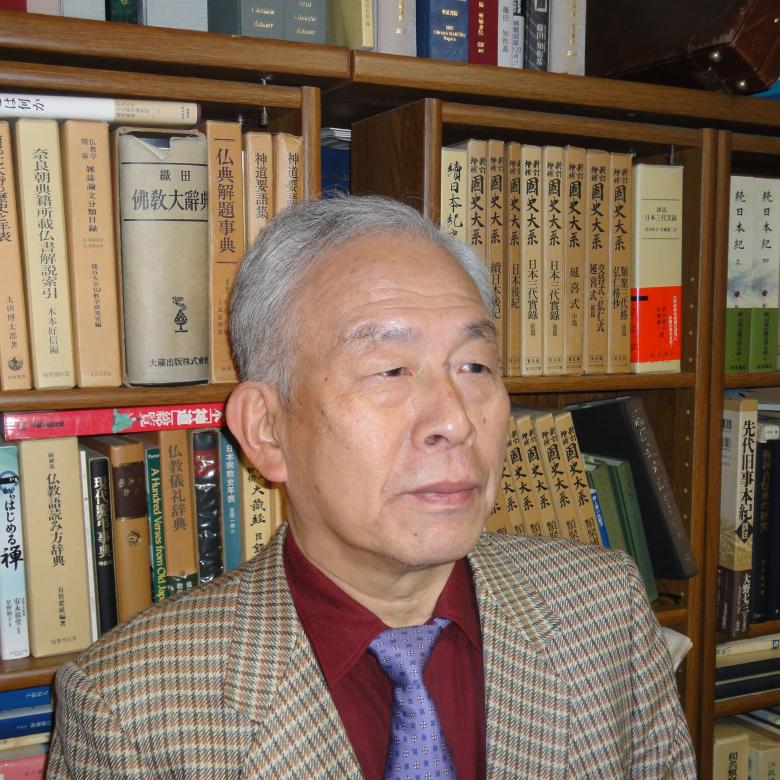 New入会金必要
New入会金必要奈良時代の人も、少し変わった人間に期待を寄せていました。「蛇を頭に巻いて生まれた子供が、寺の水田に水を引き人々を救済する。葛城山で修行した行者が吉野山まで飛行する。路傍で死んでいた乞食が仙人であった。神様の身分が嫌で仏の身分になりたかった近江の猿神。」こういう雑談116話を集めたのが奈良薬師寺の景戒で、法相宗の僧です。法相とは仏教の根幹をなす阿頼耶識(アラヤシキ)を教えます。現実を幻想と見る人間の精神活動の根幹に触れてみませんか。 日程 2025年11/3(月・祝)、12/1(月)、 2026年1/26(月)、2/2(月)、3/2(月)、3/30(月) 2026年4/6(月) カリキュラム予定 1 元興寺の道場法師(今も祭られている) 2 役の行者=山伏の起源(薬業の始祖) 3 聖徳太子が見つけた隠身の聖(片岡伝説) 4 霊異記の冥界説話と中国の冥途(悪は許さない) 5 神身離脱説話と近江の三上山の神 6 霊異記編者・景戒と法相宗
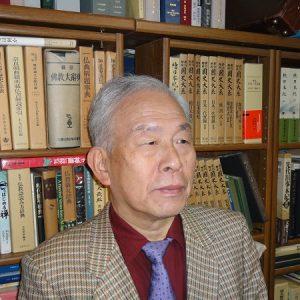
花園大学名誉教授、文学博士 丸山 顯徳
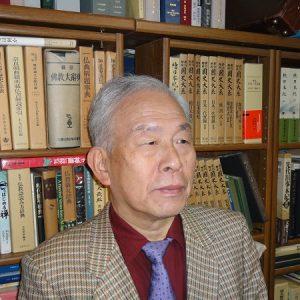
花園大学名誉教授、文学博士 丸山 顯徳
-
New入会金必要
敗者の古代史 ~悲劇の天皇・皇子女たち~
 New入会金必要
New入会金必要2026年4月開講! 飛鳥から奈良・平安時代にかけて、わが国ではさまざまな歴史が展開されてきました。 勝者となって後世に名を残した者がいる反面で、敗者となり、名前すら忘れられていった人びとも少なくありません。しかし、日本の歴史を辿る時、勝者よりも社会から疎外され脱落せざるを得なかった者、いわば敗れ滅びた者に対する共感・愛着が強いことは確かです。講座ではそうした敗者に焦点をあてて、古代史を考えてみます。 負の存在だからこそ見えてくる歴史が、きっとあるはずです。 ★2026年4月~9月のカリキュラム★ ① 4/23 (第4木曜) 伊予親王と藤原氏 ② 5/28 (第4木曜) 早良親王と桓武天皇 ③ 6/25 (第4木曜) 高岳(たかおか)親王と阿保親王 ④ 7/23 (第4木曜) 惟喬(これたか)新王と在原業平(ありわらのなりひら) ⑤ 8/27 (第4木曜) 正子内親王と檀林皇后(橘嘉智子) ご参考 ★2025年10月~2026年3月のカリキュラム★ ① 10/23 (第4木曜) 聖徳太子と山背大兄皇子 ② 11/20※ (第3木曜) 孝徳天皇と有間皇子 ③ 12/25 (第4木曜) 皇極女帝と間人(はしひと)皇女 ④ 2/26 (第4木曜) 大津皇子と大来皇女 ⑤ 3/26 (第4木曜) 聖武天皇と娘たち

京都女子大学名誉教授 瀧浪 貞子

京都女子大学名誉教授 瀧浪 貞子
-
おすすめ入会金必要常時入会可
はじめての日本書紀 ~宝皇女の重祚~
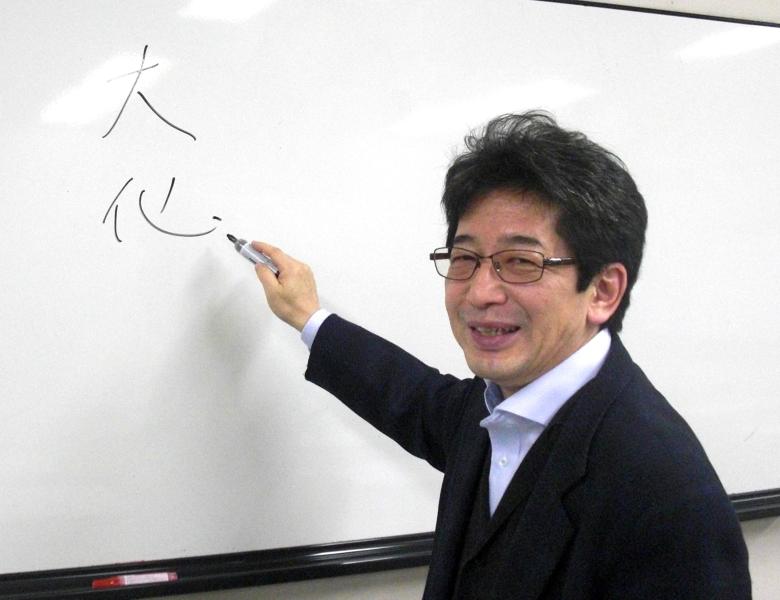 おすすめ入会金必要常時入会可
おすすめ入会金必要常時入会可『日本書紀』は、現在残される年次を記したもっとも古い歴史書です。 神代から第41代持統天皇までのできごとを記しています。読んでみると、日本という国の成り立ちを知ることができます。 今回は、はじめて開いてみようと思う方のために、斉明天皇条を中心に読みます。テキストは不要です。講師のオリジナル資料は、現代語訳で読みやすくなっています。どうぞ身軽に気軽にお越しください。 4月24日 宝皇女の重祚 5月22日 皇孫建王の薨去 6月26日 有間皇子事件 7月24日 遣唐使の派遣 8月28日 百済滅ぶ 9月25日 斉明天皇の崩御 ※予告なくカリキュラムが変更になることもありますのでご了承ください。
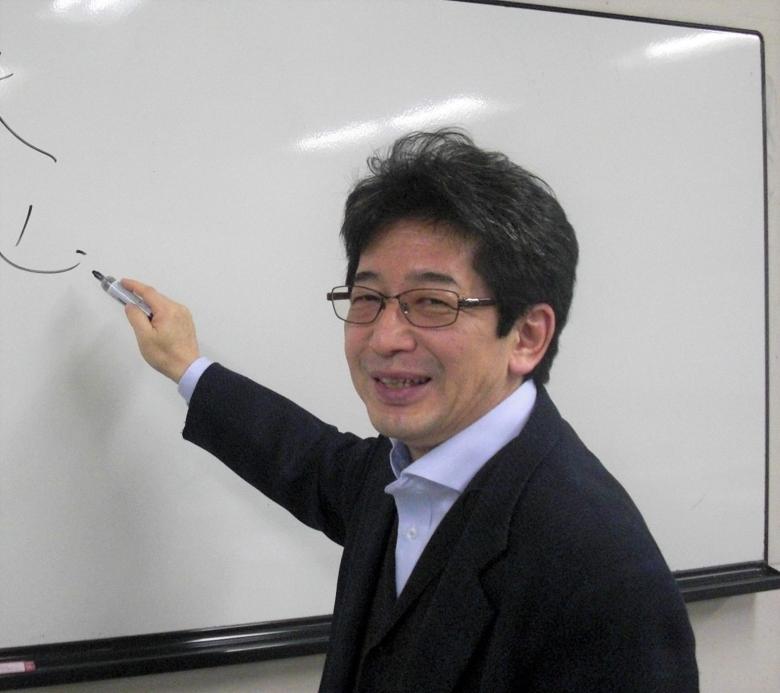
梅花女子大学教授 市瀬 雅之
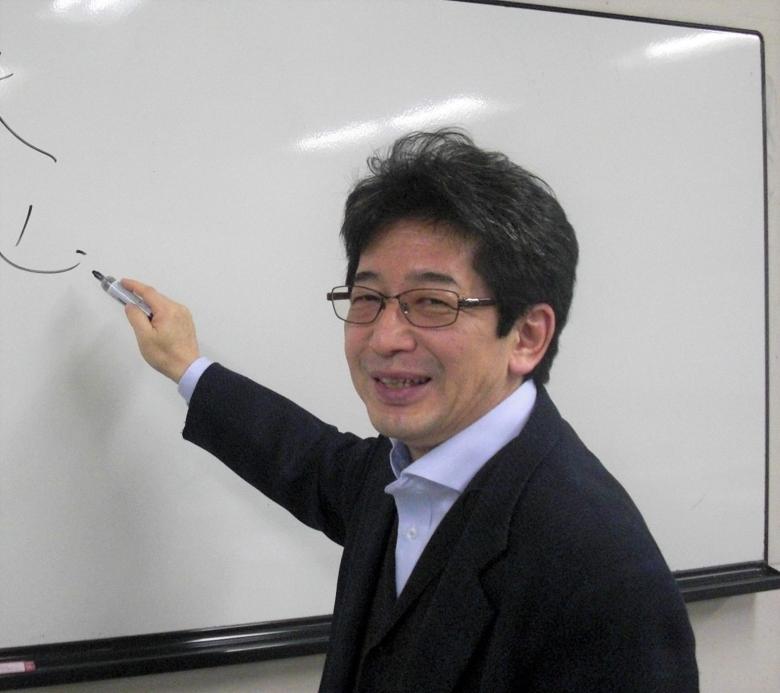
梅花女子大学教授 市瀬 雅之
-
New入会金不要見学不可
人間ドラマで読み解く 地動説の歴史
 New入会金不要見学不可
New入会金不要見学不可古代より普及していた天動説に対する科学⾰命としての地動説は、16世紀のコペルニクスから始まり、17世紀のケプラー、ガリレオへと受け継がれます。 地球が宇宙の中⼼にあって不動であると信じられていた時代に、いかにして地動説が⽣まれ、発展していったのかを、科学者たちの波乱万丈の⼈⽣をたどりながら解説します。 科学の歴史と⼈間ドラマをお楽しみください。

美術史・科学史研究家 松本 佳子

美術史・科学史研究家 松本 佳子
-
Newおすすめ入会金不要
京都の人も知らない 祇園祭の文様の楽しみ方
 Newおすすめ入会金不要
Newおすすめ入会金不要祇園祭を、もう一段深く。 祇園祭の鉾や装飾品に施された文様は、単なる飾りではありません。 そこには祈りや歴史、日本人の美意識が静かに込められています。たとえば、菊水鉾の胴掛けに、なぜ恵比寿さまだけが描かれていないのか。文様の意味を知ることで、祇園祭は「見る祭り」から「読み解く文化」へと変わります。本講座では、2回の座学で文様とその背景を学び、最後の1回は京都でのフィールドワークを通して、一般には知られていない祇園祭の準備の過程にも触れていきます。知ってから見る祇園祭は、同じ風景でもまったく違って見えるもの。 日本文化の奥行きを、祇園祭を通して味わってみませんか。 5⽉2⽇ 10時半〜12時 祇園祭の歴史と前祭の⼭鉾の⽂様 ・毎⽇⽂化センター307教室 6⽉6⽇ 10時半〜12時 後祭の⼭鉾の⽂様とフィールドワーク予習 ・毎⽇⽂化センター307教室 7⽉11⽇ 11時〜12時半 ⼭鉾町フィールドワーク ・阪急電⾞烏丸駅 ⻄改札前集合 ・毎日文化センターの旗を持っています ・動きやすい服装、筆記用具、飲み物など

Atelier華e 銀製かんざし職人 岸本 華枝

Atelier華e 銀製かんざし職人 岸本 華枝
-
Newおすすめ入会金必要
天皇陵古墳の時代
 Newおすすめ入会金必要
Newおすすめ入会金必要2026年4月開講! 宮内庁の陵墓調査官だった講師が携わってきた30年以上にわたる天皇陵古墳の調査結果を解説しながら、古墳時代を考えていきます。 取り上げる天皇陵古墳は最古の前方後円墳とされる箸墓古墳(大市墓)や、天皇陵としては最後の前方後円墳である梅山古墳(欽明天皇陵)などです。天皇陵古墳の調査を通じてわかってきた、日本の古代史を学んでいきましょう。 2026年4月~9月カリキュラム予定 第1回(4/14)「古墳時代前期の天皇陵古墳① -箸墓古墳(大市墓)-」 第2回(5/12)「古墳時代前期の天皇陵古墳② -佐紀陵山古墳(日葉酢媛命陵)-」 第3回(6/9)「古墳時代中期の天皇陵古墳① -津堂城山古墳(藤井寺陵墓参考地)-」 第4回(7/14)「古墳時代中期の天皇陵古墳② -御廟山古墳(百舌鳥陵墓参考地)-」 第5回(8/4)※「古墳時代後期の天皇陵古墳① -梅山古墳(欽明天皇陵)-」 第6回(9/8)「古墳時代後期の天皇陵古墳②-五条野丸山古墳(畝傍陵墓参考地)-」
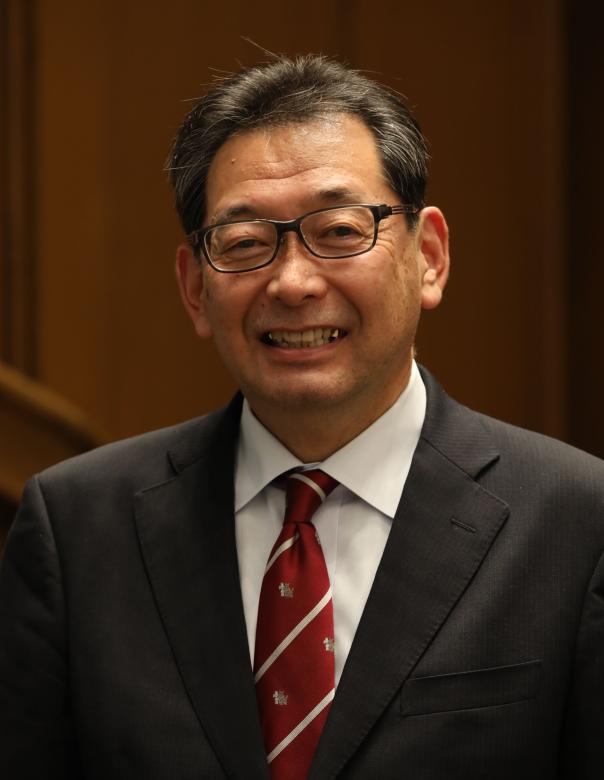
関西大学客員教授・国士館大学客員教授 徳田 誠志
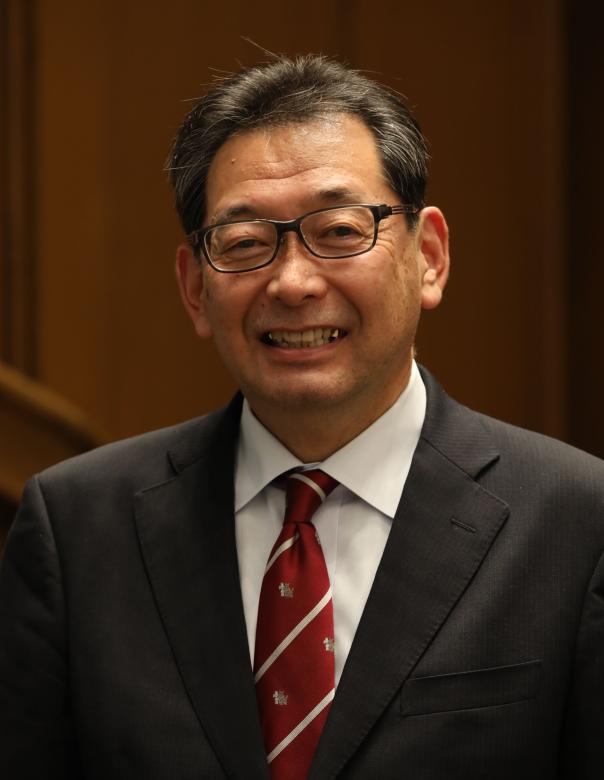
関西大学客員教授・国士館大学客員教授 徳田 誠志
-
New入会金必要常時入会可
企業家列伝
 New入会金必要常時入会可
New入会金必要常時入会可日本の著名な企業家は数多いのですが、その中でも時代性があって、まだ研究が進んでいない企業家も含めて紹介してまいります。 特に企業家の信念と革新性、苦難の乗り越え方、後継者問題、事業に成功した業界の特質などをスライドと動画をもとに見てまいります。 2026年4月~9月カリキュラム予定 1 4月7日(火) 「本田宗一郎(ホンダ)」 2 6月2日(火) 「石橋正二郎(ブリヂストン)」 3 6月30日(火)※ 「出光佐三(出光興産)」 4 7月7日(火) 「水島廣雄(そごう)」 5 8月4日(火) 「岡田茂(三越)」 6 9月15日(火)※ 「御木本幸吉(ミキモト真珠)」 ※2026年5月5日(火)は休館日のため、6月30日に日程を変えています。 ※2026年9月は、第3週の開講になりますので、お気をつけください。

大阪商業大学教授 谷内正往

大阪商業大学教授 谷内正往















